| 「吉良さん、それ、値札見ましたか」 品物をカウンターに持っていこうとしたら、ぎょっとした様子の後輩社員に声をかけられた。 立ち止まり、手の中のものに視線を落とす。猫用の首輪。肌になじむ素材は、絹とも見まごうなめらかさの仔山羊革。上品につやめく金具は、無垢の真鍮。タグにはハイブランドのロゴが箔押しされており、記された価格は、五万八千円。 「ああ、いま見たが、さすがの価格だね」 「いま見たって……それでも買うんですか?」 「気に入ったからね」 目を丸くする女子社員を、吉良は単なる光景として眺める。化粧の下手な子だ、チークの色が地肌から浮いている。手の美しくない相手なのでそれ以上の感想はない。 ふたたび品物を見下ろす。ボルドーカラーの首輪。エナメルで質感をつけられた水玉模様が愛らしい。うちの猫に似合いそうなので、これに決めた。買い物にそのほかの理由が必要だろうか? 後輩が溜息をついた。呆れと同時に諦めをこめた表情だ。 「溺愛してるんですねえ……」 私、向こうを見てきますんで、と会釈をして彼女は去る。吉良も背中を向ける。そこに至ってやっと、ああ、そういやあの子は最近わたしに興味あるふうだったなと思い出す。 吉良は基本的に、同僚や近隣住民といった近しい相手を『彼女』にはしない。失踪事件として周囲が浮足立つわずらわしさを避けるためだ。旅行者か家出娘、せめて独り暮らしの女子学生……普段の生活において無縁の相手が望ましい。仮にあの後輩が、多少見どころのある手をしていたとしても、心を打ち明ける予定はない。興味をもたれるだけ面倒だ。 この一件は、どうやらちょうどよい虫よけになってくれたらしい。昼食の誘いはすげなく断るくせに、猫の首輪に六万円を出す男。目立ちたくはないがこの程度なら、『少々マイペースなつきあいの悪い同僚』として距離を保っていけるだろう。 それにしても……はて、わたしはあれを溺愛しているのか? と吉良は内心で小首を傾げる。 確かに餌については、獣医監修と謳われた栄養バランスのよいものを与えている。でも近所のホームセンターで買える銘柄だし、極端な高級志向でもない。可能な範囲で健康に留意しているだけだ。 寝床についてはもっと簡素だ、自分の布団に入れている。布団が出ていないときは座布団の上で勝手に丸くなっているが、猫自身は座布団よりも吉良の古着の上を好むようだ。あまり外に出ない猫なので蚤の心配は少ないが、洗って清潔にはしている。 飲み水は普通の水道水。トイレ砂も猫用シャンプーもごく標準的なもの。ひとつひとつ客観視してみて、ふむ、確かにアンバランスさは否めないかと吉良は自覚する。これだけ普通に飼っていながら首輪だけが六万円の高級品だ。 でも、彼としてはやはり理由はひとつしかない。似合うだろうと思ったのだ。 だから贈りたい。装飾品にそれ以外の動機はいらない。ただ、強いていうなら――彼に自覚はなかったが――しかるべきサイズのないもの、の代わりかもしれなかった。飼育動物にとって首輪は所属のサインにもなるが、独り身ではない証明を、もしかしたら与えようとしていた。 人であれば薬指に光ったものを。  からからと玄関の戸を開ける。吉良邸は古い数寄屋造りだが、面倒がらずにこまめに油をさせば軋んだりしない。 まっすぐに立てた尾で喜びをしめし、にゃあ、と赤毛の猫がひと声鳴いた。 足音を聞きつけるが早いか玄関先で待っていたのだ。吉良が部屋着に着替えるまで、ちょろちょろと足元で落ちつかなく待つ。着替えたが早いか抱きあげろとせがんでくる。まるでおかえりのキスをねだるように。 当然のように日常のシークエンスになっているが、吉良がこの猫と暮らしはじめたのはたった数か月前だ。まさか自分が動物を飼うようになるとは思わなかった。出逢い自体は平凡の一語につきる――追うものと追われるもの。 庭掃除をするために開け放しておいた門から、何をしでかしたのか、猫がまず弾丸のように。次いで何頭かの犬がやかましく吠えながら駆けこんできた。猫は庭木に駆けのぼって逃れたが、犬はその下で喧々と騒ぎたてる。 吉良はしばらく観察し……犬に首輪がないこと、飼い主も見当たらないこと、庭を覗きこむ通行人がいないことを確認し、うるさい侵入者を消し飛ばした。樹上で震えているほうの侵入者は放っておいた。こちらはうるさくなかったからだ。追われる身への共感も、わずかならば認めてもいい。彼は先日ある靴屋で、自分をつけ狙う者たちから逃げのびたばかりだった。口封じのために店主を爆弾戦車で始末し、続いて追手どもも消すつもりだったが、状況からみてスーツの名札は見られていないと判断したため関わらぬがよしと退散した。以降、追手たちはまったく吉良の素性に気づいていない。 ともあれ猫は、そのまま敷地内に居ついてしまった。吉良が会社から帰宅してくるたび、おかえりなさいと言わんばかりに擦りよってきた。まるで十年も飼われていたかのような態度だ。そう振る舞えば上がりこめるとでも思っているのか。もし先住の猫がいたら、そいつを殺し、剥いだ毛皮をかぶってでも成り代わったのかもしれない。 動物には特に好悪の情をもたないが、野良にはおそらく蚤がいる。邪険に足で追いはらったが敷地からは去ろうとしない。まあいい、わずらわしく感じたらいつでも処分できる。猫は人懐こいわりにつつましく、払えばすぐに身を引いた。餌をもらえもしないのに健気だった。 夏が終わり、冷えゆく季節を迎えた。放っておけば風雨を凌げる場所に退避するだろうと思っていた猫は、いつまでも去らなかった。凍えながらじっと吉良の暮らしを見つめていた。庭一面に初霜がおりた日の朝、縁側の戸を開けると、底冷えする敷石にやはり猫が座っていた。 かたかた震えながら、白い息で嬉しそうに、にゃあと鳴く。 そのとき胸に湧いた揺らぎの正体を、吉良は未だに説明できない。いつものように無視すればよかった。なのに足が動かなかった。それでもあと数秒、何事も起きなければ、彼はそのまま暖かい屋内に引き返せたはずだった。 「どうも、冷えこみますねえ」 はっと顔を上げる。縁側にいる吉良へ、庭の生垣ごしに話しかける人影があった。町内会の役員をしている男性だ。 「先日の、鼠駆除の件なんですけどもね。吉良さんちはどうします?」 「ああ……ええと」 最近、別荘地帯を中心に鼠の被害が多いとかで、町内で駆除業者への依頼を募っている。地域一丸で行うほうが効果が高いため、少しばかり勧誘がしつこい。でも吉良は参加したくなかった。衛生管理には自信があるし、他人に家をいじられるのが本質的に好きではない。 断る口実が要った。それは目の前にあった。 「……いえ、今回は遠慮しておきます……ちょうど猫を飼うことにしたものですから」 小さな獣をつまみあげ、男性に会釈して屋内に入る。 その足で浴室に向かう。猫をバスタブに入れて浅く湯をはる。一度でも自分の手に爪をたてたら、その場で処分してやろうと思った。でも猫は、湯に漬けられてあからさまに硬直しつつも、吉良を傷つけることだけはしなかった。洗い終えて居間のストーブで乾かす。成獣の雌、レッドブラウンの単色の猫だ。詳しくないがアビシニアン種の血が入っているとみえる。 ふっくら乾いた猫は、戸惑ったようすで屋内をきょろきょろ見回していた。彼女としても予期せぬ展開であるらしい。いったいどういう運命の牽引力だ? 仕方がない、利用する以上は面倒をみてやろう。 炬燵に足を入れて語りかける。 「……どうした。おまえは入らないのか」 猫の尾がぴんと立った。 炬燵布団と吉良の身体の隙間にいそいそともぐりこむ。自分の場所だとでも言いたげに胸に頭を擦りつける。怖かったついでに甘えてしまえという魂胆らしい。 ひとりと一匹の新しい事情はこうして始まった。 予想外だったのは、猫には子供がいたことだ。赤毛の猫を家にあげた数日後、茶色い仔猫が庭にあらわれた。さすがに親が始終そばに付かねばならないほど幼くはない。どこか隠れ家に潜んでいたのだろう。 寒い戸外にいる子供に、母親が気を揉んで縁側をうろうろ歩きまわる。吉良は溜息をついて戸を開けた。せっかく招いてやったのに、仔猫はこちらを見るなり毛を逆立てた。 部屋にあげる以上はこいつも洗わねばならない。力ある像の存在がありがたかった。見えない力でつまみあげられ、湯に突っこまれた仔猫は暴れまわったが無駄な抵抗だ。 仔猫はしぶしぶ屋内には入ったが、成長するにつれ、あまり家にいつかなくなった。吉良に心は許さないものの、母に害をなす相手ではないと理解したらしい。人間と違って自立も早い猫の仔は、外で気侭に生きている。 対照的に、赤毛の猫はすっかり家猫になった。縁側に専用の出入り口をつけてやったが、せいぜい屋根で日向ぼっこをするくらいであまり遠出しない。広い吉良邸は猫にはなお広く、運動不足とは無縁でいられる。それ以上に、ここで吉良の帰宅を待つことが無上の幸福であるようだった。 部屋着に着替えた吉良は、通勤鞄からロゴ入りの光沢紙に包まれた箱をとりだした。がさがさと包装をあける音を聞きつけた獣が目敏く覗きこむ。 取り出した首輪を、装着する前にまずよく見せ、匂いを嗅がせてやる。一番の懸念は猫がそれを気に入らないことだった。暴れまわって勝手にはずしてしまわないよう、品物に対する不安感をあらかじめ除いてやるのが予防策だ。 結論からいえば、この猫に限ってそれは杞憂だった。『自分のための品物らしい』という理解が宿るが早いか、ぐるぐると喉を鳴らしてリズミカルに床を踏む。品物自体というよりも、この猫はいつだって、吉良が自分のために何かをしてくれた事実を嬉しがる。 「……猫は犬と違って、狭いところをくぐり抜けるし高いところにも登る。樹の枝やコート掛けにひっかけて首を吊ると危険だから、昔は首輪の装着が推奨されていなかった」 しなやかな皮革を細い首に巻いてやりながら、問わず語りに説明する。 「でもこの首輪にはちょっとした仕掛けがある。セーフティバックルだ。猫の体重程度の荷重がかかると、勝手にはずれる仕組みになっている。猫用の首輪には普及しつつあるアイデアだが、高級感を重視するハイブランドで採用されているのは珍しい……」 実用的なバックルはつややかな金具にたくみに隠され、デザイン性を損なわない構造になっている。本体に貼られたプレートはスライド式の迷子札だ。目立たないように暮らしたい吉良は電話番号の記載を少し迷った。でもどうせ名刺には書いている番号だし、自分以外にはまったく愛想をしない猫なので問題ないだろう。何かのトラブルで迷子になった場合、戻ってこないことのほうが落ちつかない。 首輪をつけてもらった猫は振りかえり、吉良の膝にすまして前足をのせた。予想どおりよく似合っている。伸びあがって見つめる瞳にはもうひとつの理解も湛えられていた。わかったわ、これであたしはあなたのものなのね。 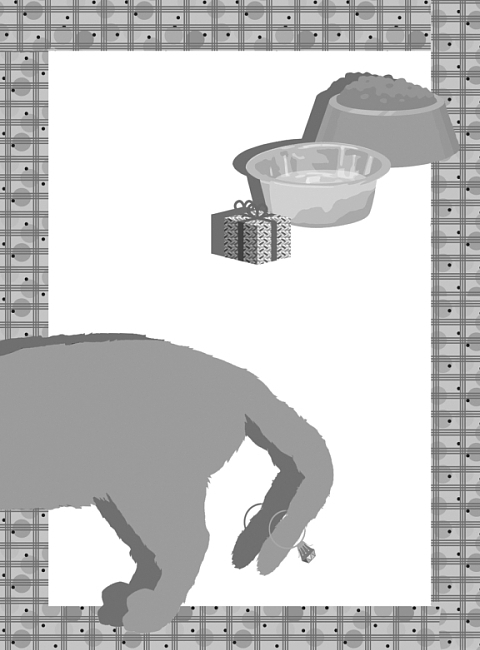 猫というものは気まぐれの代名詞だと思っていた。呼べば来ないくせに、払えば居つく。その身勝手さを尊ぶものが好きこのんで飼うのだろうと理解していた。それは自分には無縁の嗜好であるとも。 猫との暮らしは、抱いていたこれらの前提を少しばかり覆した。吉良のそばにいることだけに一途な猫だった。帰宅するたび新妻のようにまめまめしく出迎える。なにくれとなく身を寄せたがる。掃除などで邪魔なときはおとなしく控えるが、呼べばたちまち駆けてくる。犬にすら似た行動原理だ。 生活の品質を維持したい吉良は、動物と同居することにはじめのうち危機感をおぼえていた。障子を破られたり、柱で爪を研がれたり、食卓のものをいじられたり……耐えられるものではない。だが、これもよい意味で裏切られた。しつけのしやすい猫だった。行儀がよいというよりも、吉良に嫌われることをできるだけ避けようとする傾向が窺えた。 元は野良だ、まったく問題を起こさなかったわけではない。箪笥の上に飛びのった拍子に、吉良の子供時代のトロフィー群をがらがらひっくり返してしまったことがある。別に貴重品ではないが、雑然とした状態は気にいらない。吉良は飼い方教本にあったとおり、その場で「駄目だ」と叱り、しつけの合図として鼻先を軽くはじいた。 しかし翌日になって、また同じ失敗をした。数日後にも繰り返した。そのたび一貫性をもって叱った。賢い猫なので、これまでなら三回も叱ればもう繰り返さなかった。でも気に入った場所なのか、諦めが悪く、珍しく言いつけをきこうとしなかった。ついに四回目、がらがらとひっくり返した。 散らばるトロフィー群を見下ろす吉良の頭に、ある一計が浮かんだ。そこからきっちり四十八時間、彼は猫のことを完全に無視した。声をかけず、触らず、一瞥もしない。餌はきちんとやるけれど間食のたぐいは与えない。いかに迫られても居ないものとして振る舞う。 猫はあからさまに狼狽えた。尾を下げ、途方にくれて哀れっぽく右往左往した。やっぱりだ、この猫にはこれがもっとも効くらしい。気の毒なほど消沈する姿に、思わず揺れる自制心と戦いつつ、四十八時間後にやっと抱きあげてやった。 猫のよろこびようは大変なものだった。悲鳴じみた声でしがみつき、小さな舌でざりざりと痛いほど吉良の顔を舐める。以来、猫が言いつけを破ることは一度もなかった。 ただし―― 彼らのいつもの関係性が、適用されない時期があった。毎度のきっかけは猫ではなく吉良のほうにある。『彼女』を家に連れて帰るときだ。 素敵な恋人を得て、うやうやしく家まで招待すると、猫はいつも不思議とそれを察した。玄関まで出迎えにこなかった。胸ポケットに収めたまま帰宅しても同様だ。よほど臭いがしているのだろうかと危惧したが、固く血抜きをしてスプレーを吹いた新鮮な美人でも変わらない。 姿を消してはいるが、どこにいるかは解っている。晴れていれば屋根の上、天気が悪ければ縁側のすみ。虚ろを瞳に宿してじっと座っている。耳を伏せ、尾を巻きこみ、嵐がすぎるのを待つ花のように。 邪魔が入らないという意味では好都合だった。彼女たちの中には猫好きもいればそうでないものもいる。そこから会話を発展させて口説くかけひきは愉しいし、からかって拗ねさせるのも一興だ。だけどなにより大事なのは、自分のために彼女たちが崇高で、きよらかで、完結した存在であることだった。猫にじゃれつかれて傷でもつけばその調和は乱される。 彼女との同衾は甘美なひとときだったが、吉良は近頃、恋人と過ごす夜はなぜか少し冷えると思っていた。秋や冬はともかく、春や夏でも薄ら寒さをおぼえた。数か月前には存在しなかった感覚だが、差異の理由それ自体に気づかなかった。これまでと何が違うのか、何がなければ寒いのか、ほんの幼児でも理解できるあたりまえの理屈を高い知能は拒否していた。 ただ、ときどき、雨の降る夜などに。 新しい出逢いが欲しいものの、少し億劫に思うときがあった。決まって猫を抱いてうたたねしているときだ。彼の恋人はみな素晴らしい、だけどすすんで扉を叩いて逢いには来ない。必ずエスコートが必要なだけ手間がかかる。けだるい温もりとふたり、雨垂れを聞きながらうとうと眠っていると、その面倒はもう要らないのではと思う日もあった。 現実には、それは叶わなかった。いずれ募った欲望は、彼を杜王の町へと向かわせた。十数年やってきたことだ、吉良にしてみれば常態への復帰にすぎない。ただ、わずかに心臓の底を炙られるような感覚があった。それは少なくとも落胆と呼ばれるものだと、指摘してくれる者はいなかった。 ひとりの男と赤毛の猫は、北の町でしずかに暮らした。 ある年の晩秋、猫が病気をした。気づいてはいたのだ、足取りにかろやかさがない。特に多く盛ってもいない食事を残し、濡色の瞳は濁った色ばかりを映す。 ある朝、ついに布団から起きてこなくなった。申し訳なさそうなかぼそい声がシーツの奥から聞こえる。ええと、と吉良は思った。どうすべきかなと口に出したあとで、自分が少し焦っていると気がついた。 飼いはじめのころ、予防接種に連れていった獣医にひとまず電話をかける。応対した医者は容体を尋ね、おそらく猫のかかる風邪様の感染症だが、断言できないので暖かくして連れてきてほしいと言った。 「いまこのお電話で予約を入れていただければ、こちらであまり待たずに済みます」 お願いしたいと返して、吉良は希望時刻を告げた。続けて、獣医から向けられた質問は当然のものだった。 「では、そちらさまのお名前と、猫ちゃんのお名前をお願いします」 名前。……名前? 虚を突かれて口籠る。数年前に予防接種を受けたときは、著名な小説に倣ったわけではないが「まだない」と返した。向こうも聞き返してこなかった。野良猫や捨て猫を保護した人間は、長期的に飼うつもりがあれば、まず獣医に診せて健康診断や予防接種をすませる。その時点で名前がついていないケースは珍しくない。だが確かに、『ひとつ屋根で暮らしていて先日から体調を崩している』という流れで予約を受けるなら、名前はあるものと判断して当然だ。 万物には呼ぶべき名がある。あれは聖書の一節だったろうか、『言(ことば)は初めに神様とともにあり、全てのものはこれによってできた』。何にでも名前はあるのだ。吉良とて女たちを殺すときは名前をたずねる。気に入ればそのまま採用するが、気に入らなければ忘れてしまう。区分と装飾のためのツールだと考えていた。だけど本当はもっと単純だ。 名前はただ、呼びたくて付けるのだ。原始的ですらある情動が吉良には新鮮な驚きだった。 獣医が返答を待っている。ともあれ、この場で何かしら付けねばならない。無意識に視線をあげた。電話台の脇に貼られたカレンダーに目が留まる。 「しのぶ、です」 季節の絵に添えられている文言から、眼が勝手にひろいあげた文字列を告げる。受話器の向こうで予約票を書きこむ音が聞こえた。お待ちしております、と電話は切れた。 診察によれば、やはり猫のかかる類いの気道感染症らしかった。ほとんどよそと交流のない猫だが、飼い主が日々外に出ている以上はウイルスの影響を抑えきれない。「ワクチンを打っているのに重症化したのは不運でしたね」と言われ、先日まで『彼女』を避けて寒い縁側に座っていた姿を思い出し、吉良は黙った。 猫は一晩だけ入院することになった。見知らぬケージにとり残されると気づいた猫が、かすれた喉で身も世もなく鳴きわめく。吉良は考え、いつも通勤時に着けている手袋をとりだし、ケージの中に置いてやった。慣れた匂いとともに『かならず迎えにくる』という約束を得て、猫はようやく落ちついた。 秋雨のちらつく中、ひとりで帰宅する。膝にのる程度の生き物一匹がいないだけで部屋は妙に広い。 電話台のそばを通るとき、ふと思い出して改めてカレンダーを眺める。 どこぞから貰いうけた珍しくもない粗品だ。ただ月ごとのカットに、万葉集や古今和歌集から一首あしらわれているのは、それなりに通好みといえる。  高校時代の古典の授業を思い出し、試みに読み解く。 ――ひとり眺める長雨は止まず。 ――古屋の軒先ともに時を経たわたしは。 ――軒忍(のきしのぶ)の草が生い茂るがごとく。 君を偲んでいる。 翌日、退院して家に戻ってきた猫は、ペットキャリーを開けるやいなや体当たりするように吉良に飛びついた。 ほとんど唸るようにぐるぐる喉を鳴らす。害意はないのだろうが、ジャケットの生地に力いっぱい爪を立ててしがみつく。部屋着以外の服にやられて嬉しい行為ではない。でも今日は好きにさせておいた。 ぽつりと落とすように吉良は発音した。 「……しのぶ」 ゆっくり慣らしていくつもりだった。飼いはじめて数年経つが、固有名で呼ぶのは初めてだ。最初は認識すらしないだろう。何度も繰りかえして憶えさせればいいと思っていた。 猫は頭を上げた。 間を置かず、応答の意をしめして、にゃあと鳴く。 しばらく絶句する。驚きはやがて、奇妙な納得として胸の空隙におさまった。あるいは充足と呼ばれる感覚だった。 おまえはわたしの猫なのだ。 「吉良、これ要るかい?」 同僚からかけられた声に振り返ると、にぎやかな意匠の小袋が目の前で振られる。 ああ、と理解して受けとる。キャットフードの試供品だ。カメユーチェーンに業者が卸す配布物だが、店舗に送られる前におこぼれで事務方にも箱が回ってくる。 「吉良は猫をかわいがってるんだっけ? すごい首輪買ってたって聞いたけど」 「信頼できるブランドのものは値段なりに丈夫だからね。理由はそれくらいさ」 鷹揚な応答を心がける。面白みのない、目立たない、妬まれず軽んじられもしない立ち位置。 「吉良くんはいいおうちの人だからね、きみとは価値観が違うんだよ」 中年の係長にからかわれ、同僚は肩をすくめて続ける。 「それともあれか? 実は化け猫のたぐいで、夜な夜な美女の姿をとって誘惑してくるんじゃあないの? 高級バッグとか貢がされてない?」 「徳用袋の煮干しがお気にいりの庶民派の猫だよ」 他愛ない軽口で応じて、吉良はそれとなく話題を変える。 「そういえば、このキャットフードのCMに出ている女優。なんで起用されたんだろう? 犬を飼っていると聞いた気がするがねえ」 「ああ、確かにあの子は愛犬家キャラだけど、猫も飼ってるよ。動物全般が好きなのさ」 注目を逸らすために振った話題に、芸能通を自称するほかの同僚がまんまと食いついた。 動物番組のオファーが来ているだの、デビュー当時の裏話だの。話はどんどん吉良と関わらない方向に転がってゆく。慣れた操作だった。人間はたやすい。注目を逸らすのも、立ち位置を確保するのも、『彼女』として浄めてやるのも。 猫のほうがよほどむずかしいと吉良は思っていた。ききわけのよい猫なので、ひどい我儘や偏食といった手間はかからない。が、つい先日も狼狽させられた。 畳の上に猫の爪が落ちていたのだ。一本まるごとの、完全なかたちの爪。 根元から引っこ抜いたとしか思えない形状だった。人間もそうだが、爪をまるごと剥いだともなると相応の流血になる。放置できない怪我だ。吉良はしのぶの名を呼んだ。ボールの玩具にじゃれていた猫が飛ぶように駆けてくる。抱えあげて脚を調べた。すべての指に爪がついている。綺麗なものだ、血痕のひとつもない。 どういうことだ? 混乱する吉良の前で、猫が少し痒そうに、脚の先を自分の歯でがりがり喰む。人間が爪を噛むようなしぐさだ。見ている目の前で、爪が一本、ぼろりと落ちた。 慌てて拾いあげる。でもよく見れば、ひび割れて乾燥しているし血肉の付着もない。劣化して自然にとれた印象だ。 吉良は猫の生態の本をめくった。求める情報はすぐ見つかった。【……猫の爪は人間と違い、多層構造になっている。使っていた爪が古くなると、まるで脱皮するように表層だけが剥がれ、下から新しい爪があらわれる。爪とぎ材の周辺に、砕けた欠片がよく落ちているが、まるごときれいに抜けおちる場合もある……】 呆れをこめて溜息をつく。知らなかった情報だ、取り越し苦労は仕方ない。それにしても、『足の爪を剥がした』と思いこんだ程度でこうも動揺したのは我ながら意外だが。 剥がれた猫の爪は、文机の上に並べて置いてある。あることを思いついた。 引き出しを開ける。切った爪を溜めた小瓶がずらりと収納されている。コレクションの脇に並べてある予備の瓶をとりだし、蓋をあけてぱらぱらと猫の爪を納める。 ラベルを貼ってきょうの日付を書きつける。小さな硝子の空間から、爪はこの日の思い出をのちのちまで囁いてくれるだろう。何をなさっているの、と聞きたげに猫がからだを擦りつけてきた。耳の後ろを掻いてやりながら吉良は心中で返す。 なに、ちょっとした秘密の共有だ。 吉良は健康には気を遣っている。 疲労を翌日に残さない質のよい睡眠。栄養バランスを心がけた食事。健康は、信条としている『平穏な人生』の前提要項だ。おろそかにすればひび割れる。 しかし社会に出て生活している以上、どうしても周囲の影響はまぬがれない。マスクをせずに咳をくりかえす同僚から、吉良はできるだけ距離をとっていた。うがいと手洗いも慣行していた。なのにある朝、ついに発熱と倦怠感を自覚する。畜生。夏風邪をもらった。 会社に休みの連絡を入れる。陽が高くなっても寝こんだままの吉良を、常ならぬ雰囲気を察したしのぶが不安そうに覗きこむ。 吉良は自分の体質を心得ていた。発熱すると頭痛がひどくなるタイプだ。安静にしているほかないが、自律神経が乱れるせいか、ときとして己自身を扱いかねるほどの苛立ちに襲われる。凶暴な気分になる。せっかくの『彼女』をぐちゃぐちゃに踏み躙って消し飛ばすこともたびたびだ。今は『彼女』のいない時期だが、しのぶがいる。不安がった猫にうるさく騒がれたらという懸念があった。 閉めきった部屋に猫を入れ、耳栓をして、自分自身から隔離しようかと考えた。だがその必要はなかった。しのぶは黙って病床の男に寄りそった。痛みにちぢこまる姿勢を邪魔しないよう、遠慮がちに足元で丸くなり、冷えた甲にやわらかく和毛をあてた。 末端からのぬくもりに、強張る身体がわずかながらほぐれてゆく。血行がよくなり、比較的スムーズに眠りにおちた。 夢を見はじめたな、という自覚があった。 吉良は自宅の廊下に立っていた。時刻は深夜、静かで暗い。数メートル先の居間から灯りがこぼれている。ついさっきまで寝室で横になっていたはずだ。熱に苛まれた脳が非現実の家をかたどっている。 廊下を進む。居間に入ってみると人影があった。 顔を覗きこみ、ふむ、わたしだな、と思う。ただし目元には皺がより、顎は今より痩せて鋭角だ。銀縁の眼鏡をかけているし、髪にはちらほらと白い筋。 およそ五十才手前、現在から十数年あとの自分が座っていた。 夢の吉良の視線は、目の前に置かれた段ボール箱に落とされている。現実の吉良も覗きこむ。 老いた猫が横たわっている。 死の床にある、と一目で理解した。箱に敷かれた毛布には、洗っても落としきれない吐血か下血の跡。タオルに包まれた湯たんぽ。傍らにはぬるま湯のスポイト、獣医から処方された薬。横目で袋書きを確認すれば、消炎剤と鎮痛剤のみだ。完治を目指している段階ではない。 飼いはじめた当時、健康診断に診せた獣医には「おそらく三歳すぎの雌でしょう」と言われた。それから十数年が経てば当然の寿命だ。長生きしたほうだ。 夢の吉良が腕を伸ばした。敷いてある毛布ごと、すくいあげるように猫を抱きあげる。身体だけを持ちあげるよりも負担が小さい方法だ。おくるみに包まれた赤子を抱くような姿勢で、胡坐をかいた膝の上に安置する。 骨が浮いてみえるほど猫は痩せている。毛艶も悪い。呼吸はしているが、抱きあげられたのに眼を開けようとしない。意識もあるのかどうか。 夢の吉良はじっと腕の中を見下ろしている。なにか呼びかけないのか、ともうひとりの吉良は少し焦れた。やがて、単純にすぎるほどの言葉が聞こえた。 「……いい子だ」 頭を垂れ、ちいさな頭にくちづける。 単純な言葉、それはたとえば、幼子に安らかな眠りを望む大人がかけてやるものだ。 「いい子だな」 猫がほそく瞳を開けた。死に至る朦朧の中、吉良にくちづけられたことを、彼女はどうやら知覚した。老いて色褪せた身体が喜びにふるえた。くちづけがいかな感情のしぐさであるのか、猫は理解していた。 弱々しく、くるくると喉を鳴らす。男は猫を抱いたまま、もう片方の手をのべて顎を撫でようとした。だけどその腕を、猫は緩慢にすがりついて捕まえた。腕全体をひたりと抱きかかえる。あますところなく感じとるように。 夢の吉良は、猫に抱かれた腕を動かさず、指だけであやすように撫でた。猫はいっそう瞳を細めた。喉を鳴らす音は、初めて逢ったころから変わらない無垢な内面を奏でていた。すき。あなたがすき。うれしい。すき。 しあわせ。 数分を経てゆるやかに音は止んだ。 非現実に誘いこまれた側、三十半ばの吉良吉影は、黙って一部始終を見ていた。ここに至って初めて語りかける。 『死んだのか』 「死んだ」 こちらの声は曖昧な概念なのに、あちらの返事は明瞭な音声だ。ここでは夢の人物の介在する現象のほうが優先して再現される。 『どうするんだ』 「どうもしない」 五十手前の吉良吉影は、遺骸を抱いて動かない。しかし口調に淀みもない。 「庭に埋めよう。そばに花を植えてもいい。どうするかと問われれば、それだけだ」 横顔だけで振り返る。予想どおりの表情をしており、その予想が当たったことに現実の吉良は寒気をおぼえた。 「それだけだろう? 起きることは。おまえにも解るはずだ」 真実だった。それが全てだ。庭に埋め、花を植え、そして翌日いつものように出勤する。 吉良にはそれができる。できてしまう。なにひとつ動かないのか? なにひとつ起伏は生じないのか? 少なくとも父母や数多の女たちに対してはそうだった。 自分はそうできてしまうだろう。そして、できてしまう事実が音もなく精神を穿つだろう。それは飢餓の穴と化し、黒い口を開けて彼の転落を待つだろう。奇妙な矛盾だった。『平気でそうできる』のに、『平気でそうできてしまう』ことが、平穏とはほど遠い。 唇がふるえた。非現実の己自身に、なにかを言いつのろうとした。 どん、 どこかで爆ぜる音がした。 和室の天井がいつものように自分を見下ろしている。 眼を見開いた姿勢のまま、吉良はまず呼吸を整えた。派手に乱れてこそいないが、小動物のように浅くて苦しい。動悸も不安定だ。 ゆっくり布団に身を起こす。厭な夢をみた。 陽はとうに暮れていた。吉良が目覚めた気配に気づいた猫が、薄い肌掛け布団からもぞもぞと這い出る。窺うように見あげてくる。 その瞳の奥に、光の華がぱっと映りこんだ。 どん、と遠くで爆ぜる音。縁側のほうを振り返る。円を描く火の粒は消えかけていたが、まだ尾を引いてあえかな痕跡を残す。花火大会だ。 吉良邸は別荘・リゾート地帯のはずれにある。町内の掲示板に、どこかの団体が小規模ながら花火大会を予定しているとの旨があった。浜辺までは距離があるので、人々のざわめきまでは聞こえない。打ち上げ音も遠雷程度でうるさくはない。眠りから覚めるきっかけにはなったようだが。 ふらつく足元を踏みしめて立ち上がる。口内が乾いている。台所に行って作りおきの麦茶を飲んだが、あまり渇きが癒えた気はしなかった。 寝室に戻ると、布団の上にいたはずの猫が見当たらない。水でも飲みにいったのか? 首を回した視界の中で、また大輪の華がぱっと咲く。瞬間、何もないはずの縁側に、小さからぬ輪郭が照らし出された。 驚いて凝視する。儚い灯りは一瞬で去ったが、どん、と音が遅れてくるころには、吉良はその正体に気づいていた。 縁側に座っているひとりの女。 まるで昔からそこにいたように、くつろいだ姿勢で花火を眺めている。薄明の中でうなじが幽かに白い。動けずに立ちすくんでいると、再び炎の華が、女のからだの輪郭を描く。長い髪は赤みをおびて、吉良はその色をよく知っていた。 振り向いた女は困ったように微笑んだ。 立ち上がり、眼の前まで歩みよってくる。足音がしなかった。見上げる瞳は、毎日のように彼を迎えるときのものだった。知っていた。待ちわびていた。わたしのものだ。違う。やめてくれ。やめてくれ。その姿で来られたら。 人間の女の姿で来られたら。 男の指が、女の喉元に牙のように食いこんだ。痛苦に眉を寄せて、だけどはにかむように、女は笑った。深い決意はどこか恥じらいに似るのだと男は知った。 どん、 けがらわしい幸福ととろけるような絶望をこめて、手の中で生命がへし折れた。 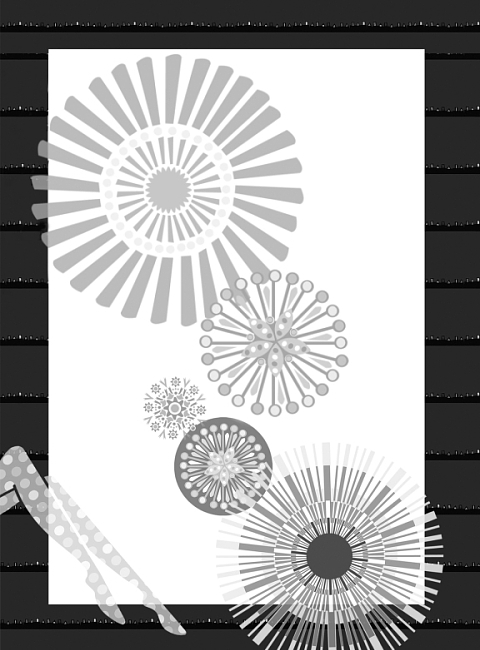 布団の上にがばりと身を起こす。 今度こそ呼吸は乱れきっている。首には脂汗。感情の乱高下に弄ばれて、しばらく現状が把握できない。ここは? 寝室? 猫は? 姿を求めるまでもなく、肌掛け布団の奥がうごめき、小さな頭が顔を出した。 自分の頬を意味もなく撫でさすり、段階的に落ちつきを取り戻す。そうだ、当然だ……あれも夢だ。一度は目覚めたと思ったが、それすらもまどろみの生んだ仮想だ。 どん、と遠雷に似たはるかな音。どうやら花火だけは現実であるらしい。 猫に視線をおとす。窺うように見あげる瞳。引きずる憔悴を追いはらい、ためらいがちに頭を撫でると、うれしそうに尾を立てた。 台所まで水分をとりに行くと、しのぶもついてきた。グラスを干すのを見守り、戻るときも後ろをついてくる。人間の女であったら言えばグラスを運んできてくれただろうか。 人間の女であったら。 ふたたびシーツに横たわり、深呼吸する。幸い熱は下がったらしい。快復を察したしのぶが、遠慮がちに頭のとなりに足をそろえて座る。手を回して背中を梳いてやりながら、差しこむ光に塗りかえられた天井に語りかけた。 「……考えたことならある」 ほんの退屈しのぎの空想だ。わたしたちはなかなか、睦まじいじゃあないかと。 まるで夫婦のようじゃあないかと。 「…………どこか別の宇宙で、」 そこまで口に出したものの、唇を曲げて吉良は黙りこむ。あまりといえばあまりの子供じみた空想だ。 ――どこか別の宇宙で。そこにはやはり地球が存在して。 わたしが杜王町に住んでいて。 わたしはわたしである以上、やはり人を殺していて。 だけど意図せぬなりゆきで、ひとりの女と暮らすことになったのだ。わたしはわたしである以上、やはりその女を殺したのだ。殺したあとできっと、こう思ったのだ。 なぜおまえは人間の女のかたちをしているのだと。 思ったのだ。強く願ったのだ。願いの産物がこの宇宙だ。わたしたちの日々だ―― 積もりゆく感覚を息にして吐きだし、寝返りをうった。 猫のいる側を向く。しのぶが首を回し、自分に添えられている手をいたわるように舐めた。どん、どどん、と爆ぜる音が間を詰めてゆく。クライマックスに向けた演出だ。 最後の大玉が夏を惜しんで咲きほこる。 猫は、猫の姿のままの輪郭を、男の眼に焼きつかせた。 あたりが静謐に沈んでゆく。熱が下がったいま、汗が冷えて少し肌寒かった。八月も終わりが近い。北国の秋は大気のはしばしに匂いつつある。 このまま、薄い肌掛けで眠りつづけるのは心もとない。でも厚手の布団にはさすがに早い。 温かいものを抱いて寝るくらいがちょうどいい。 「……おいで」 素朴な欲求に、猫がにゃあと応じた。 腕のあいだにもぐりこみ、身体を押しあてる。ひとりと一匹は隙間なく寄りそった。撫でればやわらかく指先に遊ぶ毛は、吉良をすぐ眠くさせる。質のよい眠りにおちる瞬間は、たとえどんな人間でも、無防備なただの動物になる。 夜がやさしく秘密を覆う。かれらは確かに幸福だった。 吉良吉影という男は追いつめられて死んだ。 黄金の意志をもつ若者、その年長の甥と友人たち、おそらくは町そのものに、追いつめられて死んだ。閑散とした別荘地帯のはずれ、対峙した男たちは満身創痍で戦った。通報をうけて駆けつけた女医を質にとり、殺人鬼は悪あがきを試みた。だが時の世界に入門した男の敵ではなかった。 静止世界から解放された救急車が、両者にとって不運なことに彼を轢殺した。顔を剥ぎとられると同時に頸椎を砕かれ、吉良吉影は死んだ。四十二歳になる年の夏だった。 ほぼ即死だったが、数秒だけ息があったことを、彼の近くにいた女医が確認した。もはや顔とも判別できぬ顔の、唇らしき部分が声を発するのを彼女は聞いた。不明瞭だったため自信はありませんがと前置きして、 「猫、を、」 そう聞こえたと証言した。 杉本鈴美は、なんらかの会話を交わす暇もなく、殺人鬼の霊魂が小道の奥に引きずりこまれていくのを目撃した。【振り返ってはいけない小道】は、歩む者を惑わせるべくさまざまな声や気配で誘いかける。殺人鬼が何に応じて振り返ったのかは、彼女にも解らない。 吉良吉影の最期のひとことを受けて、SPW財団の調査員が吉良邸をおとずれた。彼らが見たのは怒り狂う一匹の雌猫だった。栄養が足りていないらしく痩せていた。縁側には猫の出入り口が設えてあるので、閉じこめられていたわけではない。庭で雀くらいは狩ったようだが、町に出て残飯を漁ろうとはしなかったらしい。 猫は大変な敵意をしめしたが、吉良邸から出ようとはしなかった。 ともすれば異能者とも相対する財団職員にとって、猫の捕獲はたやすい。簡易検査がその場で行われ、スタンド生物ではないことが証明された。どこにでもいるただの猫だった。 東方仗助は、吉良邸を捜索中、切った爪が何年分も溜められた瓶を発見した。彼はその異常性に後ずさりしたが、空条承太郎はまた別のものを発見した。同じように保存された猫の爪だった。「動物の爪を引き抜いてやがったのか」と年少の叔父は憤ったが、猫の生態を知る年長の甥はそれを否定した。 そう毎回、完全なかたちで剥がれるものではないので、量ははるかに少ない。それでも数年分。恐らくは最初の一本を拾ってからずっと。切った爪の長さを測り、溜める行為がみずからを占う行為なのだとしたら、この行為の意味するものは何だろう? 薄気味悪さは抜けない。だが、引き出しにひっそりと眠っていた二種類の中身の瓶に、東方仗助はとまどいに似た形容しがたい感情をおぼえた。 猫の処遇については、虹村億泰が、父親が動物好きなので引きとって飼うと申し出た。当分は馴れると思えなかったので、一室を与えてそこで落ちつかせるつもりだった。しかし脱走した。身体が傷つくのを顧みぬ勢いで何度も窓に体当たりし、隙間をこじあけて猫は走り去った。 吉良邸の調査を終えようとしていた財団員が、舞い戻った猫の姿を認めた。しかし吉良邸は、管理が難しいとのことで遠縁の親族による取り壊しが決定している。空条承太郎は考え、吉良吉影の遺品から、どれでもいいとは思ったがとりあえず手袋を持ちだした。 吉良の遺骨の納められた墓に手袋を置く。暴れる猫を捕まえ、キャリーに納めて連れていく。蓋が開いたとたん猫は脱兎のごとく逃げかけたが、大気に混じる匂いを感じて立ち止まる。 やがて匂いの源を見つける。御影石の前に立ち、そのまま長く動かなかった。 墓所を管理している寺の住職――尼僧であった――が、最低限の面倒をみてもいいと申し出た。墓の供物を荒らされるのは困るが、見ればそうはしないし、逆に鼠どもが追いはらえてよいと言う。境内に置かれた段ボール箱が彼女のあたらしい寝床になった。 墓守りをして、猫は暮らした。手袋は段ボール箱の中に入れられていた。かつてそれが猫にした約束を知る人間はいなかった。もともと若くはないところに病を患い、一年後の夏の夕暮れ、御影石のそばで冷たくなっているのが発見された。尼僧は猫を埋めてやった。人間用の墓地には埋められないが、敷地の裏手に埋めてやった。 その夜、ある事件が起きた。 寺の近くに住む子供たちが、奇妙な影を墓地で見かけたというのだ。子供たちは三人、絵を描くのが好きな少年と、その妹たちである双子だ。 口裏を合わせている様子もないまま、同じ時刻の同じ場所に動くものを見たと証言する。大人たちは話を聞くことにした。不審者ならば警戒せねばならない。 双子の姉妹はくちぐちに言った。 「ちょっとかっこいいおとなの男のひとよ」 「そうよ、おもしろい模様の服と帽子をつけた男のひとよ」 「なに言ってるの、べつにふつうの背広を着てて、帽子はかぶってなかったわ」 「あんたこそなに言ってるの、あとねえ、女のひとを連れてたわ」 「そこはおなじね、そうよ、髪の長い女のひとを連れてたわ」 妹たちの話をじっと聞いていた兄が、呆れた素振りで舌を出す。ほらね、こいつら、人の気を引きたいからっていい加減なことばかり言うんだよ。 「ぼくは最初から、人影を見たなんて言っちゃあいない。なにか見たなら教えろって言われたから来ただけさ。墓にいたのは何でもない、ただの猫のつがいだよ。きどった感じの雄猫と、そいつとぴったりくっついてる赤い雌猫さ」 誰もが同じ話をせず、誰もが譲ろうとしない。大人たちは困り、誰かが嘘をついているのは違いないから、尼僧さんに見極めてもらうぞと言った。尼僧は正しい人だったが、厳しい人だったので三人は思わず背を伸ばした。 ひとりひとり子供たちが呼ばれて話を聞かれた。子供たちは、自分はお咎めを受けなかったので、他の二人が受けたものと理解した。その実、尼僧は全員にこう言っただけだった。 「そういうこともあるのでしょうね」 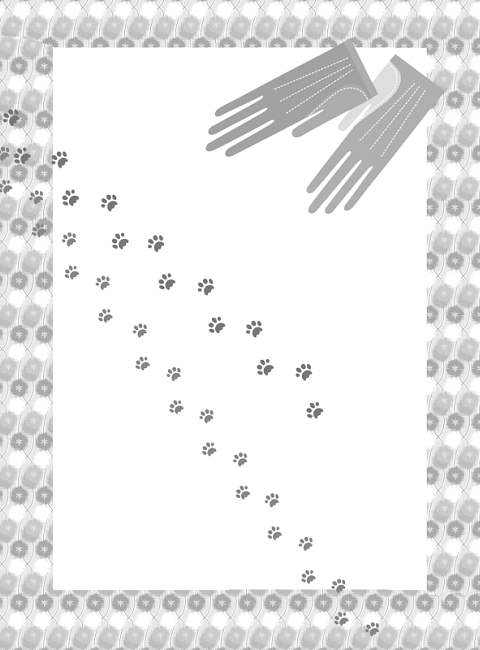 尼僧は後日、猫が寝床にしていた箱を焚きあげた。ずっと添い寝していた男の手袋も同じ炎で炊きあげた。 薄煙がたなびく宵闇に、ぱっと光の華が咲く。そういえば近くで花火大会が行われると聞いている。 どこかで猫が幸福そうに鳴いた。 尼僧は振り向いたが、どん、と遅れてやってきた花火の音に、やさしく隠されてしまった。 2019/06/05 本として発行した際の表紙 (Pixiv) |